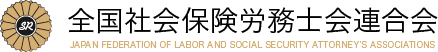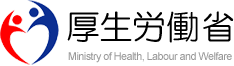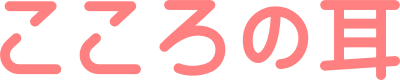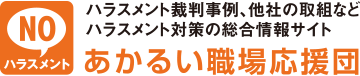私たちの生活のさまざまな場面で利用されている「電気」。産業用エネルギー源としてとても便利でかつパワーがあり、とても良く利用されています。
しかし、「見えない」「音がない」「匂いがない」という五感に訴える要素が無いため、その使用方法を誤ると大変な事故につながります。高温多湿のため感電や電気事故などが発生しやすい8月は「電気使用安全月間」です。
この期間中、電気使用の安全に関する知識と理解を深めるためのPR活動、講演会などが関係団体により開催されます。
以下、「安全月間ポスター」で職場の電気事故防止啓発を推進すると共に、電気使用安全月間(8月)について」、「チェックシート」を活用するなどを実施し、この猛暑を「電気事故無災害」で乗り切りましょう。
![]() 電気使用安全月間(8月)について20220701-1.pdf (0.1MB)
電気使用安全月間(8月)について20220701-1.pdf (0.1MB)
![]() 安全月間ポスター20220701-2.pdf (0.14MB)
安全月間ポスター20220701-2.pdf (0.14MB)
![]() 電気使用安全チェックシート20220701-3.pdf (0.37MB)
電気使用安全チェックシート20220701-3.pdf (0.37MB)
9月7日に開催予定されているセミナーの紹介です。
9月7日開催:"イメージアップ"や"業績向上"につながる健康経営とは?
今回紹介する大同生命保険株式会社様は、2019年10月より、産業医科大学・メディヴァ社とともに、中小企業向け「健康経営実践モデル」構築のための産学連携プロジェクトに取り組んでいます。
その一環として、本年9月7日(水)、健康経営の第一人者である産業医科大学の森晃爾教授による健康経営Webセミナー「“イメージアップ”や“業績向上”につながる健康経営とは」を開催します。
https://www.daido-life.co.jp/
当セミナーでは、経営者の方に中小企業が健康経営に取り組む必要性や実践方法、経営上のメリット等をわかりやすくお伝えします。
ぜひご視聴ください。
※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
※森教授は経済産業省・
熱中症搬送6月最多=1.5万人、昨年の3倍超―総務省消防庁
総務省消防庁は7月27日、熱中症のため6月に救急搬送された人数が全国で1万5969人に上ったと発表。昨年6月の4945人の3倍超で、統計を取り始めた2010年以降6月として最多。下旬に各地で最高気温が35度以上の猛暑日が続いたことが原因とみられる。
日別では、全国的に暑さが厳しくなった6月25日から30日まで連日、1日当たりの搬送人数が1000人を超え、この6日間だけで1万人以上が搬送された。
年代別では、65歳以上の高齢者が8758人と全体の54.8%を占めた。発生場所別では自宅の敷地内などの「住居」が6259人(39.2%)と最も多く、小中高校などの「教育機関」でも1184人が搬送された。
都道府県別では東京が1827人と最多で、埼玉(1381人)、愛知(1156人)が続いた。
【添付概要】
◆ 救急搬送人員の年齢区分別では、高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順。
◆ 搬送された医療機関での初診時における傷病程度別にみると、軽症が最も多く、次いで中等症、重症の順。
◆ 発生場所別の救急搬送人員をみると、住居が最も多く、次いで道路、公衆(屋外)、仕事場①の順。
◆ 都道府県別人口10万人当たりの救急搬送人員は、群馬県が最も多く、次いで福井県、茨城県、埼玉県、鳥取県の順。
![]() 令和4年6月の熱中症による救急搬送状況.pdf (1.4MB)
令和4年6月の熱中症による救急搬送状況.pdf (1.4MB)
![]() 熱中症による救急搬送人員(7月18日~7月24日速報値).pdf (0.25MB)
熱中症による救急搬送人員(7月18日~7月24日速報値).pdf (0.25MB)
以上
令和4年度 全国労働衛生週間
本年度スローガン「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」
厚生労働省は7月22日、2022年度「全国労働衛生週間」を10月1~7日に実施、9月1~30日までを準備期間にすると発表。本年度のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決定。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目である。
毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開している。
今年も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施する。
全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備するとのこと。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していく。
![]() 令和4年度全国労働衛生週間 実施要綱.pdf (0.18MB)
令和4年度全国労働衛生週間 実施要綱.pdf (0.18MB)
中央労働災害防止協会 全国労働衛生週間特別ページ
https://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/index.html
厚生労働省は、標記教材をホームページ上に公開しましたので、以下のとおり紹介します。
動画形式でとても判りやすく学べる内容になっています。是非、社内教育等でご活用ください。
資料構成:
この資料は、令和3年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業B」で作成したeラーニング用教材です。
対象者:
化学物質の取り扱うすべての労働者の方々向けです。
なお、資料4、5、8は化学物質管理者、職長など中級、上級者の方向けです。
プログラム:
【資料01-1】『職場で化学物質を安全に取り扱うために!』 MP4[23,488KB](6分1秒)
【資料01-2】『職場で化学物質を安全に取り扱うために!』(続き) MP4[29,143KB](7分5秒)
【資料02】『化学物質の危険有害性とは! ―ラベルの見方、絵表示の意味―』 MP4[26,715KB](6分43秒)
【資料03】『職場での適切な化学物質取扱い方法について ―ラベルの内容から対策を検討する―』 MP4[49,672KB](9分34秒)
【資料04】『職場での適切な化学物質取扱い方法について ―SDSの読み方-』MP4[42,595KB](12分10秒)
【資料05】『職場での適切な化学物質取扱い方法について ―法規制と危険有害性-』 MP4[45,430KB](8分38秒)
【資料06-1】『化学物質による健康障害防止の基本』 MP4[25,286KB](4分59秒)
【資料06-2】『化学物質による健康障害防止の基本』(続き) MP4[26,676KB](5分54秒)
【資料07】『物理化学的危険性(爆発・火災)による事故防止の基本』 MP4[48,565KB](8分46秒)
【資料08-1】『リスクアセスメント事例と災害対策事例』 MP4[27,145KB](5分45秒)
【資料08-2】『リスクアセスメント事例と災害対策事例』(続き) MP4[23,764KB](5分55秒)
利用上の注意:
このページに掲載の教育用資料は、事業場内における安全衛生教育を目的としており、その範囲に限り各事業場において自由に改変して利用することができます。
これらの資料は厚生労働省の委託事業によって作成されたものであり、著作権は厚生労働省が有しております。利用者は、著作権法及び関連法規を遵守するとともに、営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で教育用資料を配布、または他の製品と合わせて配布することはご遠慮ください。
以上