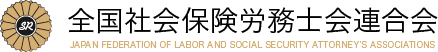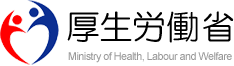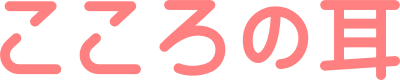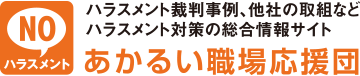厚生労働省様のクールワークキャンペンの一環で、以下期日と会場において「職場における熱中症予防に関する講習会」
都合のつく方で今まで体系的な講習会等を受講した経験がない方は、参加を推奨いたします。
1.募集対象:事業場で働く方、事業場で現場指導する方、衛生管理者等
2.募集定員:各回 100 名
3.参加費:無料
4.申込方法:添付「熱中症予防に関する講習会告知用リーフレット【確定版】p2提出
5.申込締切:2020 年 6 月 30 日(火)14:00-16:00<予定>
6.開催日程・会場
7月 08 日(水)東 京 TKP 品川カンファレンスセンター ANNEX(ホール 1)
東京都港区高輪 3-13-1 TAKANAWA COURT 3F
7月 13 日(月)札 幌 TKP 札幌カンファレンスセンター(カンファレンスルーム 6A)
北海道札幌市中央区北 3 条西 3-1-6 札幌小暮ビル
7月 14 日(火)仙 台 TKP ガーデンシティPREMIUM 仙台西口(ホール5A)
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ
7月 21 日(火)名古屋 TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター(ホール5A)
愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5CK20 名駅前ビル
7月 22 日(水)大 阪 TKP ガーデンシティ東梅田(バンケット6A)
大阪府大阪市北区曾根崎2-11-16梅田セントラルビル
7月 28 日(火)広 島 TKP 広島平和大通りカンファレンスセンター(ホール3A)
広島県広島市中区小町3-19リファレンス広島小町ビル
7月 29 日(水)福 岡 TKP ガーデンシティ博多アネックス(ジュピター)
福岡県福岡市博多区博多駅前4-11-18ホテルサンライン福岡博多駅
![]() 熱中症予防に関する講習会告知用リーフレット【確定版】.pdf (0.24MB)
熱中症予防に関する講習会告知用リーフレット【確定版】.pdf (0.24MB)
※新型コロナウイルス感染症の状況によって講習会の開催ができない場合、 講習内容をインターネット(You Tube 等)で提供する予定です。
以上
標記、日本最大の災害防止団体でもある中央労働災害防止協会から以下情報が通知されましたので、参考情報として掲示いたしいます。
中┃災┃防┃メ┃―┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃ No.335号
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 2020.5.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「第79回 全国産業安全衛生大会」「緑十字展2020in
札幌」は中止となりました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2(2020)年10月7日(水)~9日(金)に北海道札幌
当協会としては、新型コロナウイルス感染問題の状況を注視しつつ
なお、例年作成している「研究発表集」は、発表者のご理解のもと
▼詳細はこちら
![]() 20200518.pdf (0.24MB)
20200518.pdf (0.24MB)
厚生労働省は、直近版の「事業場におけるメンタルヘルス対策の取り組み事例集(2020年3月)」を公開した。
今回、業種・職種の特性に応じた取組のポイントとして、(1)自動車運転従事者の場合、(2)教職員の場合、(3)IT産業の場合、(4)外食産業の場合、(5)医療従事者(介護等)の場合をピックアップし、ポイントをまとめている。また、それら職場における具体的取り組み事例7つを紹介している。関係事業者の方は是非ご参考ください。
![]() 事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~2020.03.pdf (9.53MB)
事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~2020.03.pdf (9.53MB)
なお、法定上は常時50人以上の事業場に対する制度でありますが、50人未満の中小事業場においても、働き方改革推進及び優秀な人財確保(採用)、及び安定した生産性(病欠勤者を出さない職場)確保の観点からも、是非実施をお勧めします。中小事業場には以下のとおり助成金制度もあります。
【※常時50人未満の事業場への助成金制度紹介】
派遣労働者を含めて50人未満の事業場に対して
1.労働者1名につき500円を上限としてその実費を支給
2.ストレスチェック実施後に産業医面接指導など産業医活動を受けた場合には1事業場当り産業医1回の活動につき21,500円を上限(1事業場につき年3回を限度)として実費を支給
◆制度導入及び助成金申請にご興味がある方は、当社までご相談・お問い合わせください。
関連情報1:当社4月17日掲載【メンタルヘルス】e-ラーニングで学ぶ「15分でわかるセルフケア」
関連情報2:当社3月6日掲載【ストレスチェック】中災防が6カ国語の多言語対応を開始
以上
厚生労働省は、5月20日に開催された第86回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料を公開した。
このなかで、平行して(昼間平行、ないしは昼と夜等)複数の事業主に雇用されている労働者の労災保険給付のあり方について審議が行われ、概要が定められた。
なお、本法改正自体は令和2年(西暦2020年)3月31日に公布されており、9月1日施行の見通し。
詳細は添付PDFを参照願います。
![]() 複数事業労働者への労災保険給付について~新たな制度の運用について~.pdf (2.21MB)
複数事業労働者への労災保険給付について~新たな制度の運用について~.pdf (2.21MB)