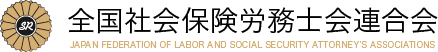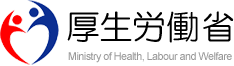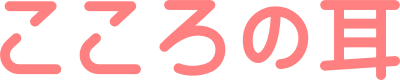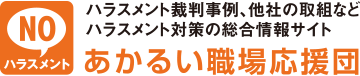2022-03-05 06:00:00
【今日の安全訓】理解していないことより、理解したつもりになっていることのほうが、はるかに危険である場合が多い。
2022-03-04 06:13:00
当社へご依頼を頂く労働安全衛生教育・講習会等の依頼書様式を改訂しました。
改訂ポイント:1.以下法定特別教育2種類を追加
・足場の組立・解体・変更従事者特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
2.酸素欠乏危険作業特別教育を、酸素欠乏等危険作業特別教育(硫化水素中毒防止も含む)に変更
詳細は以下からご確認ください。☟☟☟
労働安全衛生:安全衛生推進センター 法定教育等 安全衛生教育 ハラスメント対策 (hspc.jp)
以上
2022-03-04 06:00:00
【今日の安全訓】Don’t find fault, find a remedy; anybody can complain.
「あら探しをするより改善策を見つけよ。不平不満など誰でも言える。」
2022-03-03 06:00:00
【今日の安全訓】安全なくして会社なし。利益なくして安全なし。
2022-03-02 06:00:00
【今日の安全訓】一瞬の不注意が一生の幸福を破滅に陥れる